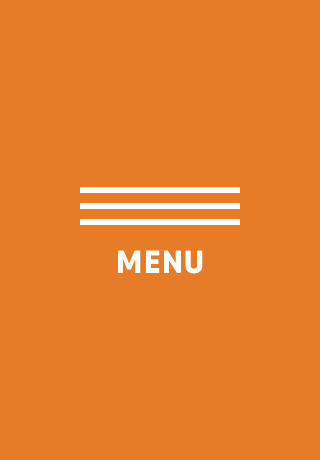【医学生が見た島根の医療】「自分で考える」ことの重要性に気づいた夏
東北医科薬科大学 新井さんからの寄稿です!
先日、当センターでの実習に参加してくれた東北医科薬科大学医学科の新井さんが、素晴らしい感想文を寄せてくれました。学生の真摯な視点から見た島根の医療、そして実習を通して得た「学びの核心」についての言葉を、ぜひご紹介させてください。

島根の先生方に共通していた「思い」
今回の実習を通して、島根県で働く先生方が同じ考え方を持っていることが非常に印象的でした。日本は高齢化と人口減少が進む中で、今まさに「総合診療医」を必要としています。島根県が全国に先駆けてその育成に取り組み、実際に総合診療医の割合が全国1位である背景には、「総合診療医のニーズ」と「教育の必要性」に対する先生方の強い思いの一致があるのだと感じました。
「ふりかえりミーティング」が教えてくれたこと
総合診療医センターの活動で特に印象的だったのは、学生の地域病院実習に対する手厚いサポートです。学生一人一人とオンラインでミーティングを行い、実習での困り事を共有し、どうすれば実りあるものになるかを一緒に考える時間があります。この「ふりかえりミーティング」を通して、学生が自分の頭で考え、主体的に学ぶことができるのは、本当に素晴らしい仕組みだと思いました。
私の大学では実習の前後に調べ学習があるのみで、目的意識を持って実習に臨むことが難しいと感じていました。その点、島根大学の実習は、「何のために地域へ行き、何を学び、今後にどう活かすか」を自分で深く考えることができる、非常に優れたプログラムだと感じました。
「日本の医師数は?」— 簡単な質問に答えられなかった私
この「自分で考える」ことの重要性を痛感した出来事があります。実習中、指導医の白石先生から「日本の医師数は?」「総合診療医の割合は?」といった質問を投げかけられました。難しい問いではないはずなのに、私は答えに詰まってしまいました。医学生である自分が、こんなにも簡単な質問に答えられないことに恥ずかしさを覚えました。
なぜなのか。
それは、私自身に「積極的に情報を得ようとする経験」が足りていないからだと気づきました。そして、情報を能動的に得るのは、プレゼン資料の作成など、「自分の頭を使って考える」時なのです。医学部に2年以上在籍しながら、その機会が自分には欠けていたことを痛感しました。
この経験を機に、これからは学内外のイベントに積極的に参加し、他の医学生や医療従事者と関わる機会を増やしていきたいです。異なる分野を学ぶ人たちとの交流も、きっと大きな刺激になるはずです。多くの人と関わり、話し合う中で、自分の頭で深く考える力を磨いていきたいと思います。
「どのように生きたいか」をゆっくり探したい
私は将来の方向性をまだ決められていません。しかし、それでも良いと思っています。進路やキャリアを決める時に本当に必要なのは、「どのように生きたいか」という問いと向き合うことだと思うからです。
まだ人生経験の少ない私には、その答えはすぐに見つかりません。これから多くの経験を積み、様々な情報に触れる中で、ゆっくりと決めていきたいと考えています。
(センターより)
新井さん、素晴らしい感想をありがとうございました。東北医科薬科大学で出会ってから実際に島根まで足を運んでくれてありがとうございます。
また、見学という短い期間で、学びの本質に迫る多くの気づきを得られたこと、スタッフ一同、心から嬉しく思います。新井さんのように、悩み、考え、そして次の一歩を踏み出そうとする学生の皆さんを、私たちはこれからも全力で応援していきます。
#島根大学 #総合診療医センター #地域医療実習 #医学生 #東北医科薬科大学 #総合診療 #地域医療 #自分で考える力 #リフレクション #島根 #出雲 #ようこそ島根へ
(ご本人の許可を得て、感想文を一部編集の上、掲載しています)